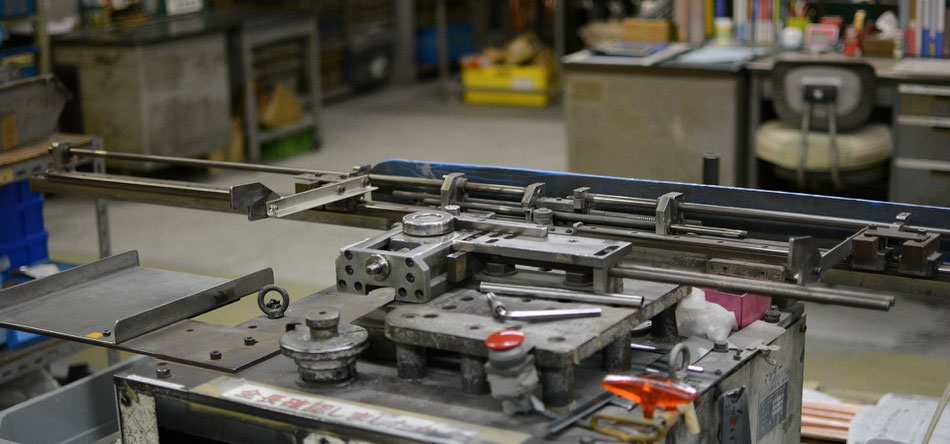事業継承/事業承継には、近づいてくる危ない業者がいます。
話を進める前に、別の意見を聞いてからでも遅くはありません。
何も問題なく営業していた中小企業に、ある日、銀行からの紹介と語る、見知らぬ男が訪れる。
男は、経営者に「事業承継」を考えているかと問う。
え?なに? ジギョー、ショ、ショーケー?
何それ?
経営者は初めて聞く言葉に、物事が呑み込めなかった。
翌日から、その男は足繁くやってきては、毎回いろんな資料を置いて行った。
いつも男が言うことは決っていた。
「早くした方がいいですよ」
「ご同業の方で、手遅れになって、取り返しの付かないことになった方を存じています」
「ご家族のためですから」
冒頭の男は「銀行の紹介」と言っていたが、経営者には覚えがない。
実は、本当に銀行が紹介したのかもしれないし、そうでないのかもしれない。
銀行が取引先企業に対して、無断で外部の業者を紹介することは、基本的にはありえない。
担当者から「今度、○○を紹介しますよ」と言われていたのかもしれない。
なにせ、最近は低金利で銀行としても預金を預かっていても儲からないので、
フィービジネスと称して、とにかく手数料を稼ぐ方向へ舵を切っている最中だ。
だから、取引先企業との日常会話においても、新しい商材を持っている仕入先だったり、
大きな取引が期待できる顧客だったり、技術力のある外注先だったり、いろんな先を
手を変え品を変え提案してくるようになった。
銀行員の仕事は、カネ勘定からビジネスマッチングになっているのだ。
だから、経営者も「また、その話か」という感じで、聞き流していたのかもしれないし、
御愛想の1つとして「じゃあ、是非お願いしますよ」くらいは言ったかもしれない。
反対に、まったくそのようなことなどなかったかもしれないが、銀行の名前を
語ったほうが最初に入り易いという安易な理由で、勝手に使ってしまう飛び込みセールスの
業者もないとは言い切れない。
最もお堅いと思われてきた銀行ですら、最近はそういう状況であるから、
中小企業に出入りするような他の業種に至っては、もう何でも有りの状況である。
証券会社、保険会社、不動産業者などという、いかにも営業攻勢をかけてきそうな
業種は勿論のこと、本来であれば飛び込み営業などするはずがないと思われてきた
「士業」が、広告業界にとっては最も伸びの大きなお客さんのセクターになっているのだ。
「士業」とは、税理士、会計士、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、
中小企業診断士などの、肩書の最後に「士」のつく国家資格を持った人たちの総称である。
近年の規制緩和で、こうした資格試験の合格者数が急拡大した。
先生の数が急増したからといっても、顧客である中小企業の数は増えていない。
それどころか、廃業が増えている状況である。
となると、新しく資格を取った士業の先生たちは、新規顧客開拓に知恵を絞ることになる。
証券会社でも保険会社でも不動産屋でも、士業の先生たちでも、とにかく新規顧客開拓は
大変だ。どんな商売でも、新規開拓は骨が折れる。
優良なお客さんは簡単には新規取引には応じてくれないし、簡単に乗ってくる先というのは
何か問題を抱えていて取引業者から見放されているケースが多いからだ。
なかなかこっちを向いてくれない優良な潜在顧客の注目を引くには、多少極端なことを言って
相手がびっくりしないと時間がかかる。だから、どうしても表現がオーバーになったり、
誇張や歪曲に近い創作がまかり通ることになりがちだ。
「え!? 何も対策を打たれてないんですか?
このまま行ったら、近い将来、大変なことになりますよ」
という調子である。
「いや、うちはそんなんじゃないから、いいよ」
といって相手にしないのが、普通の対応というものだ。
ところが、それで引っ込むような手合ではない。
とにかく、しつこい。
結局、うるさいから根負けしてしまう。
「そこまで言うんなら、話だけでも聞いてみようか」
とか、
「じゃあ、資料だけでも置いて行ってよ」
というパターンに持ち込んでしまえば、第1ラウンドは飛込み側の勝利となる。
おっとり刀の優良企業の社長が、ちょっとビビッて来た。
あれほど門前払いを繰り返されたのに、とうとう話を聞いてみようと言い出した。
こうなったらイケイケである。
飛び込みセールスの法則として、ここまで来る、つまり、最初に飛び込んでから、
曲がりなりにも提案書を提出して相手に読んでもらえる段階まで漕ぎつけることができるのは、
「千三つ」の世界と言われている。千回トライして3回しかないのだ。
0.3%である。
だから、何としてでも契約まで持ち込みたいと力が入る。
営業員にはノルマがある。個人にも組織にも目標数値が設定されいて、毎月、毎週、毎日、
上役からうるさく命令されているのはどの業界でも同じことだ。
ここに、「相手のため」よりも「自分のため」「自社のため」の論理が横行する下地がある。
最初は、「お客様の貴重な資産を守るために・・・」などと称して近づいて行くのだが、
そのうち、それは単なるお題目でしかなくなって、提案書の説明が始まったら、それ以降のフェーズは
すべてが、「契約の締結」という唯一絶対の目的のために遂行される「あらかじめ決まりきった攻撃手順」
でしかないのだ。
営業攻略作戦においては、この「あらかじめ決まりきった攻撃手順」の典型は、
「契約しないリスクの誇張」と「早期締結しない悲劇の演出」である。
「もしこの手を打たないと、こうなるかもしれませんよ」
「いま決断されないと、場合によってはこのような問題が発生しても対処できなくなります」
などと、「もし」の上に別の「もし」を幾層にも積み重ねた、虚構の伽藍を構築していく。
この作業は、あなたが判子を押すまで止まることはない。
組織目的で動いている人間は、本人の意思で止めることは最早できなくなっているのだ。
いま、中小企業のM&Aが大ブームである。
これに群がる業者が押し合い、へし合いで大混雑の状況だ
仕事が欲しくて仕方のない彼らは、盛業中の企業に押しかけて、そのオーナーに
「自社を売らないか?」と営業をかけている。
まったくその気がない人にとっては、ひどく迷惑な話だ。
しかし、「後継者は決っているのか?」「相続が大変だぞ」「ゆっくり検討している暇はない」
などと次々に波状攻撃を繰り出されると、ちょっとずつ不安になってくるのも人情というもの。
最初はまったく取り合わなかったのに、嘘も3回5回10回と聞かされていると、いつもまにか
真実味を帯びて来るから怖い。
「嘘から出た真(まこと)」とはよくいったものだ。